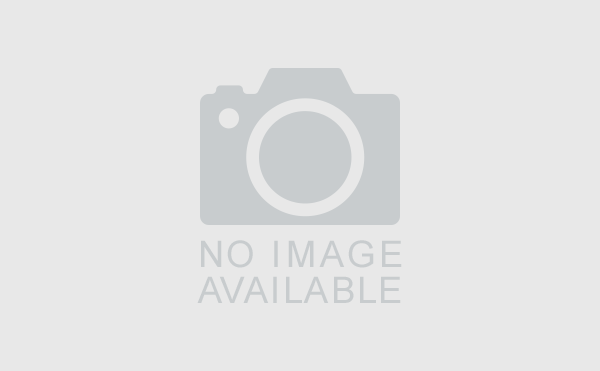令和7年 第1回市原市議会定例会議 代表質問 森山かおる
-
1.市原市総合計画[実行計画(令和7年度版)]案及び令和7年度当
初予算案について
予算編成の基本方針では「新たな総合計画を見据え、多様性・包括性・持続可能性を更に重視し、ウェルビーイングの高いまちの実現につなげる」とされています。
事業内容に目を通すと、子どもの居場所づくりや学びの選択肢確保、要配慮児童の受入れ体制の強化、基幹相談支援センターの支援体制、生活困窮者の自立支援など、マイノリティに対する新規事業や拡充事業が多くあり、市民一人ひとりに向き合い格差解消を意識した予算編成に取組まれたと感じております。
1)スクラップ・アンド・ビルドの推進について
*定量的な事業の成果・効果の見える化
高齢化の進展による社会保障関連費の増大、新たなまちづくりへの投資、公共施設の長寿命化対策としてごみ焼却施設や粗大ごみ処理施設の更新、市庁舎整備、チバニアンガイダンス施設の整備など、大規模建設事業による財政需要の対応が迫られる中で、事業の不断の見直しと優先順位付けは、これまで以上に厳しい目線で行わねばなりません。
昨年10月に公表されたR7年度版実行計画策定及び予算編成の基本方針における留意点として「事業シートの活用等により様々な検証や事業の評価を必ず行い、必要な見直しに積極的に取組むとともに、定量的な事業の成果・効果の見える化を図る」ことが付け加えられました。
これは、継続的に取組まれてきた事業のスクラップ・アンド・ビルドの徹底を、更に強化していくものと受け止めていますが、予算編成にあたり定量的な事業の成果・効果の見える化をスクラップ・アンド・ビルドにどのようにつなげたのか、お伺いします。
-
(財政部長)
スクラップ・アンド・ビルドの推進について、お答えいたします。
令和7年度当初予算編成にあたっては、市民サービスの維持・向上に必要な事業へ財源を配分するための新たな取組として、予算編成スケジュールを前倒し、前年度の決算を踏まえた経常的な経費の調査を実施いたしました。
これは、決算に基づく事業実績や成果を分析し、自己評価する事業シートの作成のタイミングに合わせ、次年度の予算編成の準備作業に着手することで、事業の方向性や課題に対する各部局の主体的な取組を予算に反映することを目的としたものであります。
この取組による成果の一例として、中小企業退職金共済掛金補助金について、人材確保支援としての費用対効果から事業を廃止し、時勢を踏まえたより有効な支援策として、産業支援センターと連携した、DX等に係る人材育成セミナーの強化を行いました。
また、予算編成過程において、新規・拡充事業等による効果や成果について、より客観的な判断につながるよう、可能な限り数値化するなど、事務改善を進めてまいりました。
その一例として、衛星画像を活用したAⅠ技術による水道管漏水調査があり、本調査により漏水リスクの高いエリアを抽出することで、人の耳による従来調査と比較し、約5400万円の削減効果に加え、早期の漏水対策による節減効果を確認し、事業化いたしました。今後も、決算検証や事業評価を行い、必要な見直しに取り組むとともに、事業の「選択と集中」、DXの推進等による行政の効率化とサービス向上など、歳入・歳出の両面から行財政改革を推し進め、これからのまちづくりと持続可能な健全財政維持の両立を目指してまいります。
-
2)市債発行について
本市の財政運営の基本指針では市債発行の上限額を50億円とし、一時的に50億円を超える発行額とならざるを得ない場合には、後年度の発行額の抑制により恒常化しないよう努めるものとしています。
市債発行額は今年度95.9億円、R7年度は88.6億円、その後も実行計画ベースでは109.9億円、115億円と増え続け、R10年度まで50億円を大幅に超える発行が続きます。それに伴って市債残高はR6年度から増加傾向に転じ、R16年度には644億円との見込みです。
残高ピーク時のH8年度944億円と比較すれば300億円も減少していますが、将来世代の負担はどうでしょうか。
市の人口推計によるとR16年度の人口は248,000人でH8年度に比べると約3万人の減少に留まっていますが、生産年齢人口の落ち込みは激しく約6万人も減少し約142,000人とのことです。
大雑把な計算かもしれませんが、市債残高を生産年齢人口で割るとR16年度は一人当り453,521円。H8年度より若干(12,427円)少ないとはいえ、事業費や執行時期が確定していない大規模建設事業は含まれていないため、負担はH8年度を上回る可能性は十分あります。予算案によりますと、市債残高はH8年度944億円をピークにR5年度末には421億円まで減少してきた現状を踏まえ、交付税措置の有無など有利な地方債の活用について検討したとされていますが、生産年齢人口に見合った世代間負担の公平性をどのように捉えて市債発行額の精査を行われたのか、お伺いします。
-
(財政部長)
本市の財政運営における市債発行の考え方については、プライマリーバランスの均衡を図るため、その発行額は償還額である公債費以下に抑制していくことで、市債残高の増加が抑えられることから、近年の公債費の推移を踏まえ、新行財政改革アクションプランにおいて、各年度の市債発行額の上限を50億円としております。
一方で、令和7年度当初予算(案)では、(仮称)八幡宿駅西口複合施設等の整備や粗大ごみ処理施設更新、市役所第2庁舎の建替えなどの大型事業の実施や建設費の高騰により、88億6千万円の市債を計上したところであり、今後当面の間は50億円を超える市債の発行が見込まれるところであります。
これらの事業は、市民生活に直結する施設やまちづくりに必要な施設への投資であり、今後、数十年間にわたり使用していくため、公平性の観点から、将来世代の方々にも負担していただくこととなる市債の活用は、必須なものと考えております。
その活用にあたっては、後年度負担に留意し、予算編成過程において普通建設事業を厳選するとともに、小規模な事業の財源については、基金等に振り替えるなど抑制に努めました。
引き続き、今後の大型事業を想定し、生産年齢人口等の人口推計による市税や扶助費などの動向を反映した、長期財政収支見通しの精緻化やローリングにより、公債費の増大が財政運営に与える影響を的確に把握した上で、市債発行額を管理していくことが重要と考えております。
あわせて、今後の財政需要の増大を見据え、貯蓄となる基金への積立強化を進める必要があります。そのため、財政調整基金残高の目標額を60億円に引き上げるとともに、次期市原市行財政改革大綱の策定において、公共施設整備基金の目標額のあり方のほか、財政運営上の健全性に関わる指標の設定や、毎年度の市債発行上限額について、検討してまいります。
-
1行政組織機構改革(案)について
1)地方創生部の解消について
R7年度には新たな総合計画を踏まえ、大幅な組織改革が行われることになっています。
公共資産マネジメントの推進を加速化するために資産経営部を新設、地方創生部を解消して交通政策課を企画部に移管、観光・国際交流課と芸術際推進室を経済部に移管、教育委員会にスポーツ文化振興の所掌事務を戻し生涯学習部にスポーツ・文化振興課を新設するなど、大掛かりな組織改革といえますが、結局、元の鞘に収まったという印象をもっております。
地方創生部については前定例会の代表質問でも申し上げましたが、目的や構成に多々疑問を感じてきたため、新たな総合計画の策定をにらんだ組織機構の改編を要望しました。そのため部の解消自体には全く異論はありませんが、市の戦略として効果検証は必要だと思っています。
そこで確認させていただきます。別々の部署に所管されていた交通政策、観光・国際交流、文化及びスポーツ振興を、地方創生部に集約したことにより、どのような成果があったのか、お伺いします。
-
(地方創生部長)
地方創生部の成果についてお答えいたします。
地方創生部は、アートとゴルフを中心とした文化、スポーツ、里山の魅力など、本市ならではの地域資源を最大限に活かし、交流人口、関係人口の拡大、定住人口の維持に向けたまちづくりを進めるため、令和4年度に新設されております。
これまで、多くの市民や関係者の皆様と対話を重ね、連携をすることで、新型コロナウィルス感染症の影響を受け中止となっていた各種文化・スポーツイベントや上総いちはら国府祭りなどを再開したほか、官民連携、自治体の垣根を越えた広域連携による芸術祭の開催、地域との連携による加茂地区のデマンドタクシーの立ち上げなど、様々な施策を展開してまいりました。
その上で、部門の集約による成果について、具体的な取り組み例をあげますと、スポーツ部門と観光部門で分かれていたゴルフ関係施策を統合し、更に発展させた「ゴルフの街いちはら」事業や、観光部門とアート部門が一体となり開催した上総いちはら国府祭りでの芸術祭オープニングイベント、地方創生担当が支援してきた地域プレイヤーと湖畔美術館を結び付けることで実現した「湖畔のマルシェ」など、各部門の事業や地域の人材、資源を掛け合わせることで、本市の新たな価値の創出につなげてまいりました。このように、地域住民の皆様、各事業者、ステークホルダーなど、多くの方々との徹底的な対話と 連携や、事業の融合に取り組んだ結果、内房総アートフェスの来場者数は21万人を超え、上総いちはら国府祭りでは、来場者数が過去最高の約34万人、そして、本市の観光入込客数が調査開始以来最高となる431万人を記録していることが成果であると認識しております。
-
もう一点確認させていただきます。
地方創生部の解消により、交通政策課が企画部に移管されます。
公共交通の利便性向上は市民ニーズのトップですが、市の公共交通の現状は運転手の労働時間の規制による2024年問題よりも前から路線バスの減便や運休が相次いで起こり、2018年に策定した立地適正化計画で示されたコンパクト・プラス・ネットワークの実現にも影響をもたらしています。交通政策を拠点形成やまちづくりと一体的に捉え、都市部に移管することも考えられたはずですが、それを敢えて企画部に移管したのは、強い思いが込められていると推測します。市長の思いをお聞かせ願います。
-
(小出市長)
交通政策課を企画部へ移管することについて、お答えをいたします。
本市の交通政策につきましては、既存公共交通機能の維持確保や、地域の実情に応じた交通手段の創設、運転士不足への対応など様々な課題が山積をしております。
私は、これら課題に対し、補助金等による事業者支援のほか、新たな地域交通手段の実証試験、小湊鐵道からの支援要請への寄り添った対応など、様々な取組を実施してまいりましたが、公共交通を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。
昨年から実施している総合計画の策定に係る対話においても、エリア別や若者・女性との対話では、「地域やまちの気になるところ」として、「移動・交通」に関する項目が数多く挙げられたところであり、多くの市民の思いを受け止めました。
この重要課題に対しましては、拠点形成やまちづくりの推進はもちろんのこと、デジタル技術の活用や、福祉、教育、産業など、あらゆる施策が関係していることを十分に踏まえる必要があります。
また、枠に捉われない発想で抜本的な解決につなげるため、庁内連携を一層密にするとともに、俯瞰的な視点とスピード感を持って取り組むことが必要であります。
このため、私は今回の組織機構改革案において、取り組むべき最重要課題と位置付け、交通政策課を企画部へ移管することといたしました。私は、総合行政推進の中心を担う企画部への移管と「担当部長」の配置により、新たな総合計画の策定段階から、これまで以上に、全庁横断的に施策間に横串を通すことで、交通課題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。
-
-
3.新たな市原市総合計画【基本構想・基本計画】骨子案について
1)総合行政の推進について
基本理念である変革と創造を推進していくために3つの戦略が掲げられ、それを具現化するために5つの方策と15の施策が打ち出されました。
現総合計画と比較すると市民に伝わりやすい言葉を用いられており、施策を46から15に絞り込むなど、シンプルにまとめ上げられたように感じています。先日傍聴した総合計画審議会では、ここまで絞り込んだ理由として「敢えて細かく設定しないことで縦割りを防ぎ部局横断的に取組む」とのご説明がありました。総合行政の推進を強化していくという姿勢は評価したいところですが、現状を見るとかなりハードルが高いと感じています。
例えば八幡宿駅西口複合施設整備後の公共施設跡地については、立地適正化計画の都市誘導区域内にあるにも関わらず、財政部と都市部での検討プロセスが見えないまま売却が進められようとしていました。
また日頃から感じていることですが、障がい福祉に係る協議会や審議会に特別支援教育という観点から教育委員会が同席することも必要だと思いますし、その逆もしかりです。
私が知る限り、県では10年以上前から障がい福祉や特別支援教育に関わる会合には、必ず双方の職員が同席していました。
後で情報を共有すれば良いということではなく、委員や市民の声を直に聴くことで思いの深さを知ることができますし、幅広い意見交換に繋がります。
これらは職員の意識改革というレベルで改善できるかもしれませんが、それさえままならない状況です。敢えて施策を絞り込み部局横断的な取組みを進めるためには、総合行政の推進の強化が必要だと考えますが、どのように強化していくのか、またそのための仕組みについてお伺いします。
-
(総務部長)
総合行政の推進について、お答えいたします。
新たな総合計画骨子案においては、現在の46の施策を15に集約することで、部門横断的に目標を共有し、施策の実効性と事業間の連動性の向上を図ることとしております。
また、庁内複合的に関わる課題や横断的に取り組むべき施策を個別戦略として位置付け、総合行政により取組を推し進めることとしております。
特に次年度は、地方創生部を再編することに伴い、様々な地域課題が各部局へ引き継がれることから、総合行政の推進がより一層重要となってまいります。
これまでも、部門管理としての「次長・主管課制度」のもと、各部門の政策立案と部門間の連絡調整をしっかり行うことで、総合行政を推進しておりますが、変化の激しい社会経済情勢の中にあっては、全般管理として、重要政策の総合調整機能をより高めることが重要であると認識しております。
このことから、今回の組織機構改革案においては、市政における重要政策や特命事項の総合調整機能、いわゆるシンクタンク機能を強化するため、企画部に「政策秘書課」を新設することといたしました。あらためて、「企画部 政策秘書課」を総合行政の推進を中心的に担う組織に据えるとともに、マネジメント サイクルとして、計画、予算、評価、改革を一体化させるなど、「トータルシステム」を機能させることにより、全庁横断的な視点と連携を深め、各施策を展開してまいります。
-
4.不登校児童生徒への支援について
このテーマについてはこれまで幾度か取り上げてきました。民間団体との連携や子どもの居場所づくり座談会の開催、またR7年度にはフリースクールの利用料及び運営者への補助も設けられ、市の取組みが前進していることを嬉しく思っています。
一方、保護者や専門家から話を伺うたびに、まだまだ多くの課題があることを痛感し、今回も質問させていただきます。
1)教員と保護者のための研修について
不登校の子どもを支えるためには、頭痛や腹痛などを訴える行き渋り期、休み始め家にこもる混乱期、休みが長期化する慢性期、外との関わりに関心を示し始め何かをやってみたくなる回復期といった4つの段階があり、その段階に応じた関わり方が重要だとされています。
行き渋り期にはムリして学校に行かせず子どものあるがままを受け入れる、混乱期には甘えを受け止め安心させてあげる、慢性期には子どものやっていることに関心を示し家の中での充実度を高めていく、こうして回復期に漸く外に出ることができます。
しかしこのような心の回復プロセスを理解していなかったために、行き渋りや家にこもり始めた時に登校を促したことで親子関係が悪化し、子どもが心を閉ざしてしまったというエピソードを何人もの方から聞いています。
また、学習の遅れが気になり通学できない日がいつまで続くのか、このままでは引きこもりになってしまうのではないかと焦る保護者の気持ちや、年度が代わり新しい担任になると、引き継ぎや知識不足といったことから対応が継続されなかったという経験談も聞いております。そこで、教員と保護者が4つの段階に応じた知識を得られる研修の場が必要だと思いますが、見解を伺います。
-
(教育振興部長)
不登校の4つの段階に応じた、教員と保護者向けの研修についてお答えします。
不登校児童生徒の対応について、不登校の背景にある要因を多面的かつ的確に把握し学校と保護者が共に支援の方向性を考え、一人一人の状況に応じた支援を進めていくことが重要であると認識しております。
教育委員会では、不登校児童生徒への支援に当たり、不登校を4つの段階という捉え方ではなく、まずは早期発見が大切であると考え、児童生徒が行き渋りを見せ始めた時の関わり方を知ること、不登校児童生徒と向き合う学校と保護者の困り感や不安を解消することなどを目的とした、教職員の研修を実施しております。
また、各学校では不登校児童生徒の状況を確認し、適切な指導方法を確認するために校内支援会議等を定期的に行っております。
保護者に対しては、「子どもの居場所づくり 座談会」を年3回開催し、子どもの状況について意見を交わすことで、保護者同士のつながりもでき、不登校についての理解を深めています。
今後、すべての保護者を対象に、子どもが不登校のサインを出した際の対応方法、学習をサポートするタイミングや方法等について教育センターだより等を活用し周知を図ってまいります。
-
2)適切な支援を考えるための実態調査について
栃木県のNPO法人キーデザインが無料LINE相談窓口の利用者を対象に、子どもの不登校が家庭に与えた影響についての実態調査をしたところ、回答者376名のうち約4人に1人が離職や休職を選択しており、「早退・遅刻・欠勤が増えた」「雇用形態を変えた」も含めると、仕事に何らかの影響が生じている家庭が約8割にも達していることが判明したとのことです。
不登校離職の問題は実際に市内でも起こっています。
しかし、もっと深刻なのは働かざるを得ないひとり親や共働き家庭です。子どもの学年や留守中の安全性の確保などの観点からネグレクトと見なされるのではと気になりながらも、後ろ髪を引かれる思いで子どもを一人家において仕事に出るしかありません。
これでは先程述べた段階に応じた関わりが持ちにくく、子どもの心の回復に影響をもたらす恐れもあります。このように不登校児童生徒への支援は子どもへの直接的なアプローチだけでなく、家庭状況を把握して幅広い観点から対策を講じなければならないと思います。そのためには実態調査が必要と考えますが見解を伺います。
-
(教育振興部長)
不登校児童生徒に係る家庭状況の調査についてお答えいたします。
不登校児童生徒については、本人への支援だけでなく、家庭状況を把握した上で、保護者等へ必要な支援を行うことが重要であると認識しております。
現在、不登校児童生徒の家庭状況については、各学校が定期的に行っている校内支援会議等において、学級担任や養護教諭、スク-ルカウンセラー等で共有しております。
また、今年度9月より導入いたしました、「市原市版 学校・保護者を結ぶコミュニケーションシート」の活用を図る中で、個別の家庭状況の把握に努めてまいります。
さらに、学校だけでの対応が難しい場合には、スクールソーシャルワーカーや子ども家庭総合支援課、いちはら福祉ネット、いちはら生活相談サポートセンター等の関係機関と相談し、連携して各家庭の状況を把握すると共に支援を行っております。
引き続き、関係機関と連携しながら、不登校児童生徒の家庭状況の確認・対応を丁寧に行ってまいります。
-
3)ストレスマネジメント教育について
不登校の兆候が見られる児童を受け入れる教室「つなぐルーム」が今年度2校に設置され、R7年度には5校に拡充される予定です。
教室に入りづらい子どもにとって安心できる場所を作ることで、不登校の未然防止や学校へ登校するきっかけの場とするというもので、文部科学省がCOCOLO プランで示している、学びたいと思った時に学べる環境を整えるスペシャルサポート設置の取組だと思っている。
16年前になりますが、私の子どもが通学していた大阪の学校に同様の教室が設置されていたこともあり、その効果については一定の理解をしていますが、不登校の未然防止としてもう一歩踏み込んで考えていただきたいと思っています。
そこで取り入れていただきたいのがストレスマネジメント教育です。
溜まったストレスを自分に向けるのが不登校、社会に向けるのが非行、弱い者に向けるのがいじめで、不登校だけでなく暴力やいじめといった行為にも繋がるストレスに向き合い、それをどう対処するかを考え、メンタルヘルスの力を身につける教育です。
文部科学省では、ストレスについての正しい知識や対処方法を身につけ、セルフ・ケアができる力を育て、困難な状況を乗り越える『生きる力』を育てる活動としており、これは全ての子どもにとって生涯通じて役立つ知識でもあります。ストレスマネジメント教育の実践について、見解を伺います。
-
(教育振興部長)
ストレスマネジメント教育についてお答えいたします。
ストレスマネジメント教育とは、子どもたちがストレスを適切に管理するための方法を学ぶ教育であり、子どもたちが様々なストレスに直面した際に、それを乗り切るための方法を身に付ける重要な取組であると認識しております。
ストレスの対処については、小学校においては保健、中学校においては保健体育の授業で学んでおります。
また、個別のカウンセリングや相談等においても、子どもたち自身が自分の感情を理解し、適切に表現できるよう取り組んでおります。
具体的には、小学校5年生の保健の授業において、心の発達のしくみや、不安・悩みがある時はどうしたらよいか、について学び、中学校1年生の保健体育の授業において、思春期の心の変化や人との関わりと自分らしさについて触れ、自分なりのリラックス方法を考えたり、信頼できる人に相談したりするなど、ストレスへの対処方法を学んでおります。
さらに、今年度は、全小学校に「いらいらしたときどうする?」という紙芝居を配布し、教職員が指導を行う際に活用しております。 ストレスへの対処については、教職員の日常の相談活動やスクールカウンセラー等による面談をとおして、子どもたちそれぞれの特性に合わせたストレスへの対処方法を身に付けさせてまいります。
-
4)学校教育の改革について
これまでは、不登校児童生徒やその保護者に係る支援について伺ってきましたが、私は学校教育も変わらねばならない時期がきていると思っています。
昨今、創意工夫を凝らした様々な学校の取組みが注目を浴びております。
1年前に市内で開催された「夢見る公立校長先生」の上映会では、通知表をなくし本人がどれだけ伸びたかを個別評価する形に変える、宿題やテストをやめる、教科学習を環境や福祉といったカテゴリー別の学習に変えるなど、子どものやる気を起こし不登校にさせない学校教育の現場が映し出されていました。
このような学校改革を成し遂げた公立学校長の熱意もさることながら、映像の中の子どもたちの生き生きとした姿が印象的で、会場にいた多くの保護者から「市原市にもこんな学校がほしい」との声があがっていました。
フレンド市原やつなぐルームといった取組みを否定するつもりは全くありませんが、学校や教室に入れなくなった子どもたちを集めて別の居場所を作るだけでなく、公教育の責任として共に学べるための方策を考えていただきたいと思っています。それが真の多様性・包括性でもあり、文科省が示した「不登校を生まない、安心して学べる魅力ある学校づくり」の真髄ではないでしょうか。
学校教育改革を進めることについて、教育長のお考えをお聞かせ下さい。
-
(教育長)
学校教育改革を進めることについてお答えいたします。
議員の話にありました、まずは子どもたちの不登校について、でございますが、解決すべき喫緊の課題と捉えております。
不登校の背景には、御承知のように学校環境、家庭環境、そして友人関係、心理的な問題など、様々な要因があり、一概に原因を特定することは難しいと考えますが、各学校においては、子どもたち一人一人の状況に寄り添い対応しているところでございます。
自分たちの学級に入りづらいなど、不登校になる前の子どもたちにとっては、特に、自分の存在を大切にしてくれる大人が近くにいるということが大切ではないかと考えております。それが自己肯定感につながり、前向きな考えや行動に移すためのサポートとなると考えます。
小学校においては、全校に配置しています心のサポーターや、つなぐルームに常駐している相談員が、また、中学校においてはやはり全校に配置したスクールカウンセラーアシスタントが窓口となってその役割を担うことで、子どもたちの安心につなげて今くださっています。
こうした子どもたちの心に寄り添う職員の配置は継続すると共に、先ほど学校の改革と言うお話がございましたけども、私が考えている学校につきましてはまずなにより管理職のリーダーシップのもとに全職員で子どもたち一人一人に関わり、誰一人取り残さない、そうしたことを進めていくことが大切であると考えています。「不登校を生まない、安心して学べる魅力ある学校づくり」を目指して私ども一丸となって、取り組んでいくということを進めたいと考えております。
好奇心を沸き立たせる教育は学びの原動力になり、自己肯定感も高まります。上映会に参加した保護者は、教育指導要領を守れば校長裁量で映画に映し出されたような学校改革ができることを知り、市原市での実践に期待しています。是非、その声に応えていだきたいと思います。
-
-
-
-
5.コミュニティ・スクールの推進について
*パイロット校の成果検証
コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校・家庭・地域が、学校の目指す教育目標やビジョンを共有し、地域と学校がより強固に連携・協働できる体制の構築を図ることを目的として、令和5年に市原小学校・市原中学校区と菊間小学校・菊間中学校区をパイロット校として導入されました。今年度は11中学校区に広げられ、R7年度には市内全中学校区(21)に導入されることになっています。
学校が抱える課題が複雑・多様化し対応に苦慮する中で、地域全体で子どもの育ちを支えていくコミュニティ・スクール導入は欠かせないものだと思っていますが、導入開始当初に伺ったシンポジウムでは、地域の人材発掘をどのように進めればよいのかなどと悩む教職員の声を聞いてきました。
また、R7年度には市内で最も多くの小学校を抱える八幡中学校区に導入されることになり、地域・家庭と学校の仲立ちを担うコーディネーターの配置については、担い手の負担を軽減するための配慮が望まれます。当局は、導入した学校の成果検証の結果を踏まえながら、地域の実情に応じ、中学校区単位をベースに市内全小中学校への導入を進めていくとしていますが、具体的にどのように地域の実情に対応されてきたのか、お伺いします。
-
(教育振興部長)
コミュニティ・スクールが地域の実情に合わせて、どのように対応しているのかについてお答えいたします。
広域な市原市においては、各地区での特色も異なることから、市内一律の取組ではなく、各中学校区で、地域の特性を生かした学校づくりや課題解決に向けた取組を進めているところです。
コミュニティ・スクールの導入にあたりましては、事前に各学校や地域がコミュニティ・スクールの意義や目的を理解し、各学校運営協議会において各学区の実情や課題を確認しあうことが重要であると捉えております。
各委員の任命にあたりましては、各中学校区の校長が適任者を人選し、その役割等について説明した上で御理解をいただいた方々にお願いをしております。
議員御指摘の地域学校協働活動推進員の配置につきましては、市原中学校区は令和5年で1名でしたが、推進員の負担軽減から令和6年度は2名体制といたしました。
また、今年度導入した辰巳台中学校区では、3小1中をカバーするため4名を委嘱するなど、これまでの検証をもとに改善を図っているところでございます。教育委員会としましては、地域それぞれの実情をしっかりと把握し、各中学校区に合わせた取組が行われるよう、引き続き、指導主事や社会教育主事による訪問を行い、熟議を重ねながら、コミュニティ・スクールの意義を理解していただいた上で、地域と共にある学校づくりに向けて活動していけるよう取り組んでまいります。
-
*コミュニティが抱える問題
地域の実情として、深刻な問題があります。
ここで令和5年度から先行的に取組んできた菊間小学校・菊間中学校区について取り上げたいと思います。
7年前に小沢議員が当局の学区外就学に対する状況把握や対応の不備を指摘し、地域コミュニティの衰退に繋がっていると苦言を呈しました。まさにその問題が昨年開催された「市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング」で浮き彫りになりました。
少子化における学校運営をテーマとした市原地区会場で、菊間小学校ではR6年度の新入学対象者72名に対し、実際に入学したのは僅か17名であったという町会長の発言に愕然としました。その方は「コミュニティ・スクールは地域が子どもたちと一緒にまちづくりをすることも大切な目的なのに、学区外就学の子どもが大半を占めコミュニティが崩壊しているのが現状。これではコミュニティ・スクールもままならない」と嘆いておられ、学区の厳格化を求めておられました。すでに学区外就学の問題については7年前に指摘しており、その間に対応されていたらこのような問題は起きなかったのではないでしょうか。未だに改善されていないのは何故なのか、ご説明願います。
-
(教育総務部長)
学区外就学への対応について、お答えします。
本市では、道路や地形、歴史的経緯等によって通学区域、いわゆる「学区」を設定し、お住いの場所によって、就学すべき学校を指定する制度を基本としております。
その上で、国からは、地域の実情に即して、学区の弾力的運用が求められていることから、子どもたちや保護者に事情がある場合や、通学距離等の地理的条件から見て困難な場合などにおいては、指定した学校以外の学校に通学することができる運用を行っているところでございます。
ご質問の菊間小学校につきましては、学区である大字古市場の一部区域において、学校までの距離等を踏まえ、石塚小学校にも通学できることとしており、当該区域にお住いの子どもたちは、この制度により、石塚小学校に通学している状況にあります。 このように、学区につきましては、就学すべき学校を指定する制度を原則としつつも、子どもたちや保護者のことを考えた運用を図っており、保護者等からも安心につながる、負担軽減につながる等の御意見をいただいているところでありますので、引き続き、この考え方を基本に対応を図ってまいります。
-
しかし実態は部活動など定められた許可理由以外の理由が主で、越境している生徒の多くが自宅から登下校していることは周知の事実です。それを知っていながら放置していたとしたら、許可した責任が問われるのではないでしょうか。地域の悲痛な声に、今後どのように対応して、コミュニティ・スクールを進めていくのか、伺う。
-
地域の声に対応したコミュニティ・スクールの推進について、お答えいたします。
「市原型」のコミュニティ・スクールの特徴としましては、各地域の声や状況等に対応するため、各中学校区単位を基本に、学校と地域の様々な人材や伝統行事、各種団体などをコーディネートする「地域学校協働活動推進員」を配置し、学校運営協議会の委員として参画することで、この学校に通う子どもたちがどのように育ってほしいか、そのためには何ができるかを考えていただいております。
このことから、地域学校協働活動推進員が地域ごとに特色ある活動に取り組み、幅広い地域住民等の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えていくことにより、コミュニティ・スクールを核とした、新たな地域ネットワークの形成を目指しております。
この実現のためには、地域学校協働活動推進員が学校や地域の皆様と議論を重ね、情報や課題・ビジョンを共有し、協働しながら、学校や地域のニーズを捉えた子どもたちへの学びや体験等を提供していくことが重要となります。
教育委員会としましても、地域学校協働活動推進員への伴走型の支援をするため、継続的にスキルアップに向けた研修のほか、推進員同士の対話の場や連携した活動、情報の共有化を行っているところです。 コミュニティ・スクールの導入により、学校運営や教育活動だけでなく、子どもたちの地域活動への参加や地域住民同士の交流の広がりなど、「地域コミュニティづくり」の充実にもつながることから、今後も全市展開に向けた計画的な導入を行うとともに、活動を通じた魅力ある学校と地域づくりに取り組んでまいります。
-
-