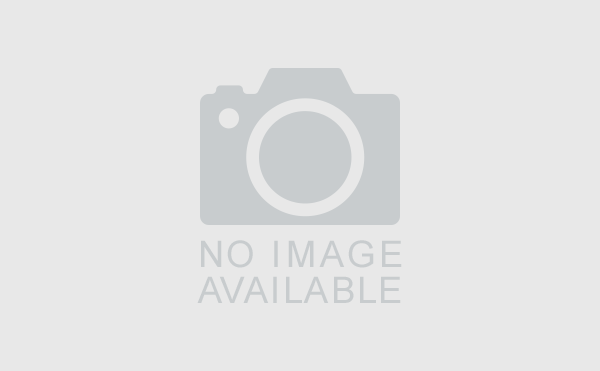令和7年 第2回市原市議会定例会議 個別質問 小沢みか
-
五井会館の利活用について
◆ 12年間放置された五井会館の状況
五井会館は供用開始以来44年が経過し、老朽化が著しい状況にある。
平成25年度(2013年)に五井支所等がサンプラザ市原に移転して以来、実に12年間も利活用の方向性が検討され続けてきた。
平成30年度(2018年)のサウンディング型市場調査は不調に終わり、令和2年度には「子育て世代にとって魅力的な交流拠点」「アートを活かしたプラットフォーム」など抽象的な方針が示されたが、具体的な進展は見られなかった。
そして令和4年度、市は庁内外のプロジェクト会議により3つの利活用方針(*キャリア教育 *学力格差の克服や教養教育 *国際交流)を定め、同方針に則って令和5年度から今年度まで合計約4,500万円もの予算を投じ実証事業を続けている。◆ 市民不在の利活用方針と実証事業
しかし私は、市が策定した「利活用方針」や実証事業の進め方には大きな疑問を抱いている。
実証事業は当初1年間の予定が3年間に引き延ばされ、内容は単発のイベントに終始している。効果検証も示されず、「実証」とは呼べない状況であることはこれまでの委員会質疑でも明らか。
さらにこれらの動きについて多くの地元住民や事業者がご存じなかった。『もし知っていたら、協力や連携ができたのに』という当然のお声もあがっている。
また、国際交流協会すら蚊帳の外であったという事実も驚くべきこと。そもそも、市のこれまでの多文化共生施策の状況から鑑みて、唐突に利活用方針に国際交流が盛り込まれたことに対し、私は当初から違和感を抱いていた。
このようないわば「内向きの会議体」で策定された方針に基づき事業を進める市の姿勢は、市民との信頼関係を著しく損ねるもの。地元や関係者の理解と協力を得られないまま進められる事業に、一体どのような実効性があるというのか。◆ エリアマネジメントの視点で仕切り直しを
また、五井会館の利活用が進まない根本原因は、公共資産としての明確な位置づけや戦略の欠如にあるのではないか。
同会館は、都市再生整備計画や立地適正化計画・都市機能誘導区域に位置し、都市構造再編集中支援事業といった国庫補助の活用が可能な優位性を持っているが、プロジェクト会議でそういった観点で検討されたとも思えない。
従って私は、もうこの際一から仕切り直した方が良いのではないかと考える。
つまり、地域住民や関係者等との対話を再構築した上で、中心都市拠点の活性化に資する施設として包括的ビジョンと具体的な戦略のもと、真に市民生活に必要な機能の整備・誘導を進めていただきたいが、ご見解をお聞かせ願う。 -
(資産経営部 部長)
五井会館につきましては、五井駅周辺の中心都市拠点に位置しており、駅に極めて近い立地から、非常に高いポテンシャルを有する公共資産と認識しております。
そこで、市ではこれまで、拠点まちづくりを進める中で、五井駅西口に集積する五井会館・梨ノ木公園地下駐車場・梨ノ木公園を一体的に捉え、リノベーションやキャリア教育、国際交流といった視点で施策の実証を行い、新たな価値の創造に向けて取り組んでまいりました。
一方で、建築から40年以上が経過し、施設や設備の老朽化が著しく、安心・安全に関する懸念もあることから、今後も引き続き利用するためには、大規模な施設改修や設備更新を要し、多額の費用がかかると見込んでおります。
このことから、市といたしましては、公共資産の高いポテンシャルを最大限発揮した利活用を図るため、資産経営の観点から、持続可能なまちづくりの推進に向け、ハード面も含めた更なる有効活用を検討する必要があると考えております。
検討に当たりましては、近隣の梨ノ木公園地下駐車場等を対象に含めるなど、施設単体での検討に限定することなく、立地適正化計画等を踏まえたエリア全体を俯瞰した視点を持ちながら取り組んでまいります。
また、公民連携も重要なことから、様々な主体との対話を積極的に行い、より地域に貢献できる機能誘導の実現を目指し、関係部局と連携して取組を進めてまいります。一から仕切り直すという意味と受け止めた。(部長頷く)
-
◆ 一方で市民活動の場を奪い続ける市の責任
ここで特に申し上げたいことがある。
五井駅西口では、市民活動センター(アイホット)が平成28年3月をもって突如閉鎖された。
利用されていたボランティア連絡協議会(約40団体・500名が加入)の方々は、8年が経過した現在もなお事務局機能や活動場所の確保にたいへん苦慮しておられる。メンバーの高齢化が進み、自家用車を利用できない方も増えており、駅近の施設を求めるお声もあがっている。
さらにサンプラザ市原のリニューアルでも活動場所を失うNPO法人等もあり、同様の現象が生じている。市は新たな総合計画の素案においても「人の力を活かす」と謳いながら、よりによって中心都市拠点で市民が活動するステージをむしろ奪っている状況は、計画と実態の乖離を示唆するものではないか。
私はここで特定の団体に便宜を図って欲しいと主張するつもりはないが、市は五井会館の利活用方針を策定する過程で、これらの声に耳を閉ざしていたことは明らか。
そこで伺う。
今後、五井会館の利活用を検討するにあたり、このような状況をしっかりと認識した上で進めていただきたいが、ご見解をお聞かせ願う。 -
(資産経営部 部長)
市民活動団体につきましては、その目的、活動内容、メンバー構成等により多様な活動が行われており、事務局機能や活動場所に関しましても、団体ごとに様々な形態で運営されているものと承知しております。
このことを踏まえ、五井会館の利活用の検討に当たりましては、公平性等に配慮しつつ、機会を捉えながら、市民活動団体等と丁寧に対話を行ってまいります。
対話にあたっては、現状をしっかりと捉えて課題を整理した中で検討を進めて、目指す利活用の方向性について、御理解をいただきながら取り組んでまいります。例えば、ウエルコミのような「企業と連携した市民活動促進事業」を五井会館でも実現させることができれば財政面でも理想的とも思う。
-
◆遊休施設の暫定的な活用について
次に、利活用されるまでの間の暫定的な対応について伺う。
五井会館は年間約1,000万円もの維持管理費がかかっているが、特に1、2階は基本的に使用できない状態。
五井大市の際には例外的に貸し出されるが、トイレは故障しやすいからと使用が禁止され、多くのボランティアや市民が不便を強いられた。実証事業の予算4,500万円があればとうに改修できたのではないか。市の施策の優先順位には首をかしげざるを得ない事が多すぎる。
私は3年前一般質問で、低未利用公共施設について当面の間の利活用策を検討するよう提言したが、未だに進んでいない。
そこであらためて、市内の遊休施設の暫定的な利活用が容易になるよう、早急に使用許可の基準など全庁的な仕組みを設けることを要望する。
そして五井会館については設置管理条例などを言い訳にするのではなく、速やかに具体的な手立てを講じて頂きたい。
ご見解を伺う。 -
(資産経営部 部長)
当初の目的が失われ必要性が薄れた資産や、長期に渡って事業未着手である資産など、低未利用資産の暫定的な利活用の推進は、財源確保や維持管理費の縮減、地域の活性化など、様々な可能性を考え、公共資産マネジメントの観点から、必要な取組であると捉えております。
本市では、「公共資産の適正な管理及び利活用に関するガイドライン」を策定し、公共資産の適正な利活用を推奨しておりますが、様々な施策を展開する中で、より重要度や緊急性が高い事業を優先的に取り組むことで、低未利用資産の利活用に力が及んでいない場合もあると認識しております。
このことから、今後、ガイドライン等の見直しなど、低未利用公共施設の暫定的な利活用方策を含め、資産活用に関する仕組みを構築し、更なる公共資産の有効活用を推進してまいります。
なお、五井会館につきましても、仕組みの構築の中で庁内関係部門と調整を図り、検討してまいります。例えば八幡宿駅周辺の八幡東中や、複合施設整備に伴って閉鎖する公民館・支所など、都市拠点でも遊休施設は増えている。ぜひ早急に対応していただきたい。
今年度、資産経営部が復活したが、今度こそ財産管理に終始する事なく、市民の期待に応える真のマネジメント機能を発揮されることを期待している。
-
企業主導型保育事業への支援について
◆ 企業主導型保育の役割
企業主導型保育は、待機児童対策と多様な働き方への支援を目的として、平成28年度に内閣府が始めた制度。児童福祉法上は「認可外保育施設」になるが、内閣府・子ども家庭庁による厳格な指導・監査のもと、認可施設と同等どころかそれ以上の厳しい基準をクリアしている。
市原市内には現在9カ所の企業主導型保育施設があり、定員は合計149名。うち地域枠として64名分が確保されている。さらに企業枠も実際は市内のお子さんの利用が多く、本市の待機児童解消に大きく貢献してきた。
市の「こども計画」においても保育の確保方策として明示されており、特に0~2才児の受け皿として不可欠な存在。◆ 企業主導型保育に対する市の扱いの現状 市の認識は
しかしながら、市はこのような企業主導型保育施設に対して、認可施設と比べ著しく不当な格差を放置している。
例えば、第二子以降の0~2歳児の保育料無償化といった保護者への支援や、保育士への給与加算「いちはら手当」などの市独自の支援事業は、企業主導型保育施設の保護者や保育士は対象外とされている。
また、市のホームページなど広報においても認可施設と同等に扱われず、保護者が情報を得にくい状況にある。
私は、こうした状況が「認可施設と財源の出所が違う」などという一元的な理由で正当化されていることに、到底納得がいかない。
企業主導型保育施設は、夜間や土日、一時預かり・短時間利用が可能など、多様な働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供することができる。
また、市の入所審査を経ず直接申し込むことができ、パート、自営業、フリーランスなど正社員以外の働き方をしている人も受け入れやすいメリットがある。
このように企業主導型保育は、まさに「認可保育施設以上の保育水準」と「認可外保育施設の多様性・柔軟性」を兼ね備え、本市の子育て支援に欠かせない役割を担っているのではないか。
そこでまず伺う。当局は、企業主導型保育事業の役割やこれまでの待機児童対策への貢献をどのように認識しているのか。 -
(子ども未来部 部長)
企業主導型保育事業は、従業員の多様な働き方に応じた保育を提供する企業に対し、運営費・施設整備費等を支援することを目的として、国が平成28年度に創設した制度です。
本事業の実施にあたっては、子どもの受入れについて、当該企業の従業員の子どもを対象とする「企業枠」に加え、地域の子どもを受け入れる「地域枠」の設定ができるものとなっております。
現在、市内には9つの企業主導型保育事業所があり、うち8つの施設で「地域枠」を設け、令和7年4月1日時点で35人の利用者がいるものと承知しております。
市といたしましては、本事業について、企業が実施する従業員に向けた保育サービスという側面だけではなく、「企業枠」、「地域枠」による子どもの受け入れを通じて、本市における待機児童の解消に、多大なる御貢献をいただいているものと認識しております。実際、特別な支援が必要なお子さんや複雑な事情を抱えるご家庭からのご相談も多く、こうした方々の最後の受け皿にもなっている。
-
◆ 保育の2025年問題と企業主導型保育の展望
保育の需要は今後減少傾向に向かうとされており、保育士不足と相まって、施設の淘汰が進む可能性が指摘されている。
このような環境下で生き残るのは、働く保護者の多様なニーズや地域の実情にマッチした、質の高い保育を提供する施設。
私が企業主導型保育の関係者の皆さまから感じるのは「平等な条件のもとで、保育の質で勝負したい」という切実な願い。
当局が、企業主導型保育を本市の保育提供体制に欠かせないものとして認識しているのであれば、質の向上に専念できる環境の整備が必要ではないか。
そこで伺う。
当局は「子ども計画」において今後4年間は保育ニーズが逓増すると見込んではいるが、保育業界が構造的な転換期を迎えていることを踏まえ、新たな総合計画のスパンで捉えた時にどのような対応策を考えておられるのか。
また、企業主導型保育事業に対し、認可施設との不当な格差を解消し「平等なステージ」で保育の質を高めていける環境を早急に整えていただきたいのだが、ご見解をお聞かせ願う。 -
(子ども未来部 部長)
令和7年3月に策定いたしました市原市こども計画では、潜在的なニーズの顕在化により市域全体の保育ニーズが、計画最終年度である令和11年度に向けて増加していくものと想定しております。
その後は、保育施設の整備が進んだことに加え、少子化の進展により、地域の実情によって違いは生じるものの、市全体としては、保育ニーズが減少に転じる可能性があるものと考えております。
保育施策については、少子化等、人口減少に対応しながら、子ども・若者が自分らしく輝き、明るい未来を切り拓くまちを目指すためにも、これまでの待機児童の解消に向けた量の確保から、今後は、地域のニーズに対応した質の高い保育への転換を促せるよう、更なる保育士の確保や環境整備を推進してまいりたいと考えております。
次に、企業主導型保育事業における保育環境については、認可施設同様、市内に住むお子さんをお預かりいただいていることから、さらに保育の質を高めていくことが求められているものと認識しております。
このため、まずは施設にとって何が必要なのか把握するため、現場との対話を実施してまいります。
その上で、企業主導型保育事業への支援については、未就学児を預かる施設・保育サービスが多岐にわたることを踏まえ、未就学施設全体のニーズを捕捉し、支援のバランスにも配慮しながら、最適な支援について検討してまいります。同時に、保育士への研修の強化や、地域の保育施設が連携して保育のノウハウを共有しあう仕組みなど、保育事業全体の質の向上を支援する体制整備にも引き続き取り組んでいただきたい。
-
八幡宿駅西口複合施設の整備に伴う風水害時の対応について
現在、八幡宿駅西口では支所や公民館機能を含む複合施設と認定こども園の建設が進められており、令和8年3月の供用開始が予定されている。
今年3月に開かれた住民説明会では参加者から多様なご意見が出され何れも気になるところではあるが、今回は生命に関わる喫緊の課題・風水害時の対応に的を絞り質問する。◆ 建設地の災害リスク
建設地は、洪水ハザードマップによると、最大規模の降雨による河川の氾濫や高潮において、最大3メートルまで浸水する可能性があるとされている。
さらに、内水ハザードマップも示す通り、建設地前の白金通りは、これまで幾度となく大雨により冠水してきた。
事実、昨年9月の豪雨時は、歩道を含む通り全体が川と化し、周辺では大規模な交通渋滞が発生した。早期開設避難所である八幡公民館への避難はおろか、職員の参集すら困難を極めたことは記憶に新しいはず。◆ 防災拠点と避難所機能をどうするのか
複合施設は大雨等警戒時に早期開設避難所に指定され、大規模災害時には現地連絡本部が設置されることとなっている。しかし、複合施設は現在の公民館・支所より更に海岸や運河沿いになる。市原地区・特に駅東側の住民が、海岸に向かって駅を超え白金通りを渡って避難するという選択は、どう考えてもありえない。
また、そもそも道路が冠水した場合に職員が迅速に参集できるのかという根本的な課題も残る。
私は整備計画当初より、公共施設をわざわざより危険な場所に移転させるという市の判断に対し疑義を呈してきたが、これまで当局からは危機感のかけらも感じた事はない。
そこであらためて伺う。
複合施設における風水害時の早期開設避難所の代替施設の確保や現地連絡本部のあり方について、早急に検討する必要があると考えるがいかがか。
供用開始もいよいよ間近に迫っていることから、今度こそ明快なご答弁を求める。 -
(総務部 部長)
市原市地域防災計画に基づき、風水害時の適切な避難行動を促し、早期避難による市民の安全を確保するため、市内の各地区1箇所程度に早期開設避難所を設置することとしております。
昨年9月3日に発生いたしました時間雨量76ミリの大雨の際に、早期開設避難所である八幡公民館の前面道路が冠水により通行不能となり、市民の安全な避難行動に支障が生じました。
このことを踏まえ、今後、同様な事象が発生した際の対策として、早期開設避難所の代替施設を速やかに開設できるよう、近隣の小学校の施設管理者との調整を終えたところであり、今後、地元町会等との調整を経たうえで、本年8月からの運用開始を目指しております。
次に、現地連絡本部につきましては、本区域は、想定最大規模の洪水や高潮などによる浸水リスクが想定されておりますが、複合施設の構造上2階部分を使用することで、本部機能を維持することができるよう設計はされております。
しかしながら、道路冠水で水が長時間引かないことにより、職員が参集できない場合も想定されます。
そのような場合には、業務継続計画、いわゆるBCPで、予め作成している代替庁舎リストから、最寄りの安全な場所を選定し、現地連絡本部機能を確保してまいります。
-
◆立地適正化計画における防災の主流化と市の責任
これまでの過程において、行政が最も重視すべき「市民の生命を守る」という視点が後回しにされていたことは、非常に残念でならない。
自然災害の頻発化・激甚化に対応するため、令和2年に都市再生特別措置法の一部が改正され、コンパクトシティの形成において、防災の観点をより重視する取り組みが必要となった。この法改正の趣旨からしても、今回のようなイエローゾーンへの新規立地は本来避けるべきであったが、それでも推し進める以上、市はこの複合施設が抱える災害リスクに今度こそ真摯に向き合って頂きたい。