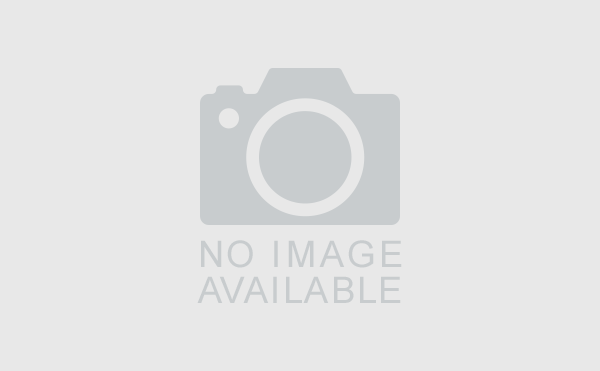令和7年 第2回市原市議会定例会議 個別質問 森山かおる
-
1.新たな総合計画におけるアートの位置づけについて
*アートが市の魅力になるのか?
先日の全員説明会で提示された市原市総合計画[基本構想(素案)・基本計画(素案たたき台)]によると、2035年に目指すまちの姿として5つの分野があり、その一つ「魅せる・楽しむ(交流・自然)」に、ゴルフやアート、歴史・文化、スポーツ、里山を市の地域資源及び魅力と位置づけています。
ゴルフについては市内小学生の体験授業や、手ぶらでゴルフという企画を実施し、国内最大数のゴルフ場を持つ本市ならではの魅力として位置づけることは十分理解できます。ゴルフ場利用者数も2026年度目標値180万人に対して2023年度177万人という成果をあげています。
上総国分寺や更級日記はまさに市の誇れる歴史・文化であることは誰もが納得するところです。
スポーツや里山については、ラグビー日本代表やトップチームにも利用されているスポレクパークは国内外からの評価が高く、養老渓谷などの豊かな自然は市民意識調査でも高評価を得ています。
しかしながらアートについては、10年以上前から芸術際を開催し「アートのまちいちはら」のブランド化を図ってきましたが、市民には定着しておりません。
2023総合計画成果検証においては、活躍指標「市内の観光施設を訪れたことのある市民の割合」の2026年度の目標値80%に対して57.2%。成果指標では「小湊鐵道利用客数(1日フリー乗車券・観光列車乗車人数の合計)」の目標値8万人に対して3.7万人。トロッコ列車の故障ということもありましたが、それを踏まえたとしても目標値と大きな乖離が生じています。
このような状況にもかかわらず、新たな総合計画に、市原市の地域資源及び魅力としてアートを位置づけた理由について、お伺いします。 -
(企画部長)
新たな総合計画におけるアートの位置づけについて、お答えいたします。
市では、アートを日常的に感じられるまちづくりによって、魅力、共感、愛着を創出し、交流人口や関係人口を増加させ、持続可能なまちとすることを目指し、各種事業を展開しております。
アートと様々な地域資源を融合させ新たな価値を創出する課題解決型の芸術祭として2014年からスタートしたアート×ミックスをはじめ、空き店舗等を活用した「牛久リ・デザインプロジェクト」や、内田・里見・平三・月出などの閉校した小学校を活用した地域ならではの取組など、年を追うごとにアートが日常となるまちへと広がってきております。
また、これまでの取組を通じて、市原湖畔美術館をはじめとした常設展示作品も拡大し、通年でのイベント等への来訪者の増加に加え、アーティストの地域への定着、菜の花プレーヤーズや大学、県・近隣自治体との連携などにより、交流人口・関係人口の拡大にもつながるなど、「アートのまち」としての市原が、市内外に認知されてきているものと考えております。
このことから、「2035年に目指すまちの姿」の一つである「愛着と誇りが生まれ、交流が広がるまち」の実現に向け、今後も活かしていく重要な地域資源の一つとしてアートを掲げたところでございます。
-
16億円も投じたが市民から評価されていない
そもそもアートの活用目的は過疎化する市南部の課題解決や活性化でした。ところが今や他市との合同開催によりエリアが拡大し、一体何を解決したいのかが曖昧になってきているように思えてなりません。先日の市民経済常任委員会においても同様の意見がありました。
しかも同委員会で示された資料に「地域課題解決の実践が必要」と記載されていたことには驚きました。
芸術際を始めた当時は、自治体が行うアートトリエンナーレは珍しく注目されたかもしれませんが、今や他の自治体もどんどん取組み始めており、相当な魅力付けが必要です。
しかし、そのために多額の事業費を投じることに市民は納得しません。
R5年度市民意識調査報告書によると、市原市の魅力として上位を占めているのは、東京近郊で緑の多いゆとりある住環境、養老渓谷など豊かな自然、ローカル線の小湊鐵道と里山トロッコ列車、国の天然記念物であるチバニアンの地層、国内で最も数が多いゴルフ場、国内有数のコンビナートの夜景。これらは令和元年度の調査から不動です。
一方アートに関しては、令和5年度までに芸術際を3回も開催してきたにもかかわらず、15項目中14位で2.5%の評価。会場となっている地区の評価も低く、加茂地区で9.5%、南総地区では5.3%に留まっています。
アート関連事業に約16億円も注ぎ込んできたというのに、市民から認識されていないアートを市の魅力と位置づけるのは無理があるのではないでしょうか。
そこでお伺いします。
過去の市民意識調査や現総合計画の成果検証の結果をどう受け止めているのか。また、投じた約16億円の費用対効果をどのように捉えているのか、お聞かせ願います。 -
(経済部長)
はじめに、アートによる取組に関する成果検証について、お答えいたします。
市民意識調査の結果では、「いちはらアート×ミックスを本市の魅力だと思う」と回答した人の割合が他の項目との比較では低い状況にあり、一方で、総合計画の成果検証においては、アートイベントの展開が基本構想の補完指標である「観光入込客数」の増加に寄与しているとの評価を受けております。
加えて、これまでに開催した芸術祭での来場者アンケートでは、いずれの回も約9割の方から好意的な評価をいただいております。
このようなことから、芸術祭の来場者には、本市が「アートのまち」として認知され、アートが交流人口の拡大による地域経済の活性化に大きく寄与していることを、評価いただいている結果であると認識しておりますが、芸術祭に来場したことのない人、アートに興味がない人からは、評価いただけていないことを勘案しますと、市のアートを活用したまちづくりへの取組に対するプロモーションの不足がその要因であると捉えております。
次に、費用対効果につきまして、お答えいたします。
芸術祭の開催を核にアートを活用したまちづくりの最大の目標は地域の活性化であり、経済波及効果だけでなく地域課題の解消、地域住民の活力向上など、まちづくりの視点から総合的に捉えるべきものと考えております。
これまでの芸術祭では、市の費用負担に対しおよそ2倍以上の経済波及効果を生み出しており、さらには、閉校となった校舎の利活用や、商店街の賑わいの創出など、単なる芸術祭の開催に留まることなく、本市の関係人口の拡大と地域課題の解消が進んでいること、そして何より地域の皆様の主体的な活動が増えていることなどから、一定の成果があったものと捉えております。
議員ご指摘の費用対効果の視点は、芸術祭という行事を開催するためには必要なことではあると認識しておりますので、次の芸術祭の開催においては、事業の目的と効果をしっかりと認識した上で取り組んでまいります。
さらに、より多くの市民の皆様に芸術祭の楽しさを知っていただき、「アートのまちいちはら」の意義をご理解いただけるよう、プロモーションの強化や魅力あるコンテンツの提供に取り組んでまいります。
以上です。
-
以前質問した時は、市内の経済効果というのは把握されていませんでしたが、先ほど2倍以上の経済波及効果があったというのは、市内でということで理解して良いのでしょうか。
-
(経済部長)
お答えいたします。
これは、市が負担した額に対する2倍以上の波及効果という形になります。
-
その経済波及効果というのは、市内の経済波及効果ですかと、お聞きしているのです。
-
(経済部長)
お答えいたします。
これまでの芸術祭、4回開催しておりますけれども、それぞれの開催のエリアが違う部分があります。
その中で、経済波及効果については、それぞれの回数に応じて市が負担した費用に対する効果が、2倍以上あるというような形になります。
以上です。
-
では、2倍というのは市内の経済波及効果ではないということですね。もっと客観的な検証を冷静になってしていただきたいと思います。
*位置づけを見直すべき
市民意識調査の目的は、重要施策の企画立案や部門計画の見直しなどに反映させるものです。例え来場者や関わっている市民の満足度が高くても、それは元々関心を持つ一部の人たちの声であり、ベースにすべきは市民意識調査ではないでしょうか。
また、新たな総合計画策定にあたって実施したエリア別・若者・女性による対話でも本市の魅力としてアートはあがっていませんでした。それを総合計画に掲げることで今後も億単位の費用が投じられるのではと懸念しています。実際先月に、千葉県・市原市・木更津市・大多喜町で連携した芸術際を令和9年に開催するために、3市で約2億円を負担するとの報告があり、先走りし過ぎているように思えてなりません。
市原市観光動向調査及び分析業務委託調査報告書においても「アートのまち」としての認知が浸透していないことが挙げられており、これは市民意識調査を踏まえると市民もこのままの路線継続を望んでいないと言うことです。
そこで、新たな総合計画におけるアートの位置づけを見直していただきたいと思っています。
例えば市原市教育大綱改定骨子案では基本目標5「ふるさとへの愛着と誇りを育む歴史遺産・文化芸術の継承と活用」があげられており、
現代アートをあくまでも芸術の一つとして捉え、総合計画においても教育大綱と同様に「文化芸術」と表現しては如何でしょうか、見解を伺います。 -
(企画部長)
お答えいたします。
新たな総合計画の2035年の目指すまちの姿「愛着と誇りが生まれ、交流が広がるまち」では、これまでの「アートのまち」の成果等を踏まえ、ほかとの差別化を図る本市の強みとして、賑わいと交流の創出に資する地域資源の象徴的な例示として「アート」という表現を用いております。
基本構想素案の分野5「魅せる・楽しむ」を実現するための施策の方向性としましては、「アートを日常的に感じられるまちづくり」のほか、歴史や文化の魅力創出の面から、「文化芸術の保存・継承」や「創造的な文化芸術活動への支援」「文化芸術を担い、支える人材の育成」などを掲げており、こうした取組により、市民の愛着や誇りの醸成、交流と賑わいの創出につなげてまいります。
なお、新たな総合計画における基本構想、基本計画、個別計画などの記載の内容につきましては、それぞれの計画等の役割り、位置付けなどによって、どのような意図でその表現を用いるのか、市民の皆様にしっかりと伝わるよう取り組んでまいります。
以上です。
-
これまでにアート関連で約16億円も注ぎ込んできたのに、なぜ浸透しないのか、客観的に判断していただきたいと思います。また、このまま継続するのであれば、市民意識との差と今後かける費用のバランスを見極めていただくよう要望します。
-
2.市のトイレ整備について
1)観光地における整備について
ゴールデンウィーク前、市の南部に出向いた時に飯給のトイレに立ち寄った。13年前に著名な建築家によりデザインされた世界一大きなトイレ。正式名称は「Toilet in Nature」でグーグルマップには「自然の中のトイレ」と表記されているが、市民には1千万円のトイレと認識され注目を浴びたアート作品です。
ところが敷地に入ってみると、ガラス張りのドアが全く動きません。後に当局に確認したところ、管理受託者からドアが開きにくいとの報告が入り、設計者の了解をとり修理依頼を行うと伺っております。
飯給と同じ建築家がデザインした牛久駅前のトイレは、完成後たった2年でドアの不具合が生じ修理が必要となりました。
このようにデザイナーズトイレを作って注目を浴びたところで、早々に故障したり不具合が生じると設計者の了解を得たりする手間がかかります。今後は維持管理しやすく修理期間も短縮できるよう、一般的な仕様にすべきではないでしょうか、当局の見解を伺います。 -
(企画部長)
観光地におけるトイレの整備について、お答えいたします。
本市では、観光振興ビジョンにおいて「誰もが訪れたくなる おもてなしのまち いちはら」を掲げ、観光客に選ばれる観光地づくりに取り組んでおります。
このような考えのもと、観光客にご利用いただく公衆トイレにつきましては、2014年の芸術祭の開催にあわせ、単なるトイレの「設備」ではなく、里山の景観と調和したアート作品の一つとして設置することで、芸術祭の来場者に楽しんでもらうだけでなく、新たな「観光スポット」、「おもてなしのツール」として、整備を進めてまいりました。
現在では、小湊鉄道沿線の6箇所にアートの要素を取り入れたトイレを整備しております。
アート化したトイレの効果の一例としましては、小湊鉄道の飯給駅前に設置しておりますトイレ「Toilet in Nature」いわゆる世界一大きなトイレや、牛久駅の「里山トイレ」は、現在開催されている、大阪・関西万博の会場デザインプロデューサーを務める藤本壮介さんが設計したものであります。
飯給のトイレは設置から10年以上が経過した今でも、先週金曜日のニュース番組でも取り上げられておりますが、度々メディアで紹介されるなど、本市ならではの魅力として情報発信や集客に大きく寄与しております。
なお、こうしたトイレにつきましては、地域の皆様の手により丁寧に維持・管理していただいており、修繕等が必要となる場合にあっても、アート作品としての価値を損なわないよう適切に対応しております。
以上です。
-
トイレは使えなければ意味がありません。現在開催されている大阪万博でもデザイナーズトイレのランプがつかず、初日から一部で使用できなくなったことが報道されていました。
見た目のデザインに凝るよりも、心地良く使えるトイレにしていただきたいと思います。
-
2)公共施設における男女格差解消について
*市の認識
3月末、VONDS市原により改修工事を終えた臨海球技場の内覧会に伺いました。
コンセプトは「先ず、女性と子どもと高齢者、障がいをお持ちの方に優しいスタジアム」とし、特に印象に残ったのがトイレ改修でした。男性用よりも女性用の面積が大幅に広げられており、設計者に伺うと「昨今ではこれが当たり前」と話されていました。女性トイレに列ができるのは当然とされてきた男性主導型の社会から、女性視点を重視する時代へと移り変わったことを実感しました。近年、高速道路のサービスエリアや商業施設などにおいても女性用が多く設置されるようになり、これは単なる面積の平等ではなく、「待ち時間の公平」を追求する考え方への転換であり、社会全体の男女格差に対する意識の変化の表れとも言えます。
では、公共施設はどうでしょうか。
そこで先ず市庁舎の状況を調べてみました。男性用の小・大便器数と女性用の便器数を比較すると、最も格差が大きいのはこの本会議場や会派室がある棟で、各階共に女性用は和式一つしかないのに男性用はその6倍。第2庁舎は各階共に男性用は女性用の3倍。これら建設当時が如何に男性社会であったかを思い知らされました。
一方、比較的建築年数が浅く7年前(2018年)に併用開始となった第1庁舎、現在建築中の八幡宿駅西口複合施設、これから整備が進められる新庁舎の設計では、男性用は女性用の1.5~1.8倍となっており、時代の変革に伴って男女比が改善されてきたことを感じています。
そこで確認させていただきます。
公共施設のトイレの男女格差について、どのように認識されているか、お伺いします。 -
(資産経営部長)
公共施設におけるトイレの男女格差について、お答えいたします。
公共施設のトイレについては、市内の公共施設の多くが高度経済成長期に整備され、当時の社会的背景から、男女間において便器等の数に差があるものと認識しております。
また、その後の社会情勢の変化の中で、洋式化への対応は行ってきたものの、限られたスペースでの改修では、トイレの数の減少や通路を狭くせざるを得なくなるなどの新たな課題も出てきており、トイレについては十分な改修がなされず、ご不便をおかけしている施設も多くあるものと捉えております。
このような課題については、性別だけでなく、年齢や障がいの有無など、多様性が尊重され、誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目指す中において、解消すべき課題であります。このことから、現在の施設整備にあたっては、ユニバーサルデザインの中で、施設の特性に応じて、男女間における便器等の数の適正化を図るとともに、多目的トイレの整備を推進するなど、誰もが快適に安心して利用できるトイレ環境を整える必要があると考えております。
以上です。
-
公民館や支所、保健福祉センターなどを調べてみましたが、築年数が30~40年以上経過している施設の男女格差が大きいとは言え、簡単にリフォームできるものではない事も承知しています。
そこで今後の考え方について伺います。*今後の方針について
山口県萩市では、公共施設のトイレにかかる整備方針を策定し、独自に基準を設けています。
学術団体である公益財団法人空気調和・衛生工学会が示した事務所や病院・劇場などの男女比を基にして、公共施設の新築や増改築において男性小便器数と女性便器数の比を概ね1対2とするというものです。これは女性用トイレの渋滞を解消する目的で定められ、公共施設には庁舎も含まれています。
この萩市の方針は2017年に決定したもので、それ以降に本市で建設された公共施設に当てはめると、第1庁舎は1対1、最も新しい歴史博物館で1対1.1。現在建設中の八幡宿駅西口複合施設では1対1.3、新庁舎の現設計においては1対1.2という状況です。
一方、10年以上前にオープンした市内の大型商業施設は1対1.8。施設の違いはありますが民間との差を感じられずにはいられません。
そこで伺います。
萩市の整備方針では、便器数の他に、洋式化の優先順位や温水洗浄便座・多目的トイレの設置、清掃が簡易な乾式床などについても規定されており、市原市においてもこのようなトイレ整備に係る基本的な方針を定めるなどして、男女格差解消を図っていただきたいのですが見解を伺います。 -
(資産経営部長)
公共施設のトイレに係る整備方針について、お答えいたします。
公共施設の整備にあたっては、より良い公共施設を目指し、他自治体の取組や民間施設の事例について研究するとともに、市民の皆様との対話を通じて、多様な意見を取り入れながら進めることを基本に取り組んでいるところです。
その中で、トイレについては、公益社団法人 空気調和・衛生工学会が定める基準をもとに、建物の用途や想定利用者数、利用時の待ち時間など、施設の特性を十分に検証の上、必要な便器等の数を算出し、整備しているところでございます。
市といたしましては、引き続き、施設特性を踏まえ、利用者の男女比を考慮し、きめ細かな配慮を持って整備を進めることで、公共施設のトイレにおける男女格差の解消に努めてまいります。
以上です。
-
今後予定されている文化交流施設の設計にあたっては、男女格差解消を図り、並ばなくても済むトイレにすることで、施設評価が上がり集客につながることを期待しています。
その際には、是非女性職員の意見も聴取していただくようお願いします。